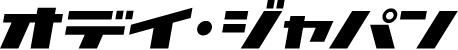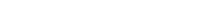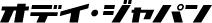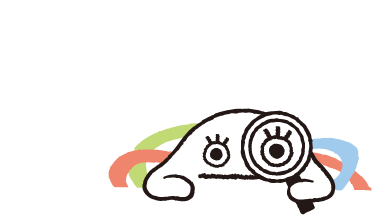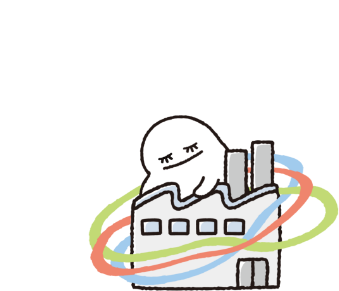飲食店や食品工場などに設置が義務づけられているグリストラップ。
排水中の油脂や食品残渣を分離して流出を防ぐための重要な設備ですが、清掃を怠ると悪臭や詰まりといった問題を引き起こし、さらには法令違反につながることもあります。
本記事では、グリストラップ清掃の適切な頻度について、関連する法律や条例を交えながら解説します。
Menu
グリストラップ清掃の基本と目的
なぜ定期清掃が必要なのか
グリストラップは、排水中の油脂や食品残渣を沈殿・分離して下水へ流さないようにする装置です。
これらは日々発生するため、定期的に清掃しなければ油脂の固まりや食品残渣が腐敗するなどして、悪臭や詰まりを引き起こします。
さらに、放置し続けると排水管の腐食や害虫発生にもつながります。
グリストラップ清掃・管理の詳細についてはこちらの記事をご覧ください。
衛生面だけでなく法令面のリスクも
悪臭や害虫が発生するほどの状態は、保健所の衛生基準に抵触する場合があります。
また、排水に油脂が多く含まれたまま流出する状態が続くと、「下水道法」や「水質汚濁防止法」に違反する恐れもあります。

法律で求められるグリストラップ清掃の考え方
直接的な「清掃頻度の法定義」はない
現在、下水道法や水質汚濁防止法では、「グリストラップを何日に一回清掃しなければならない」という明確な規定はありません。一方で、排出する水質基準を守る責任は各事業者にあります。
つまり、基準を満たすために必要な清掃管理を行う義務が課されていると言えます。
管理基準は自治体ごとに定められている
多くの自治体では、「週1回以上の清掃」や「油分の堆積が一定量を超えないように管理すること」といった独自の基準を定めています。
この基準は地域によって異なるため、チェーン展開する業態は特に注意が必要です。
参考:東京都下水道局の案内
実務的に推奨される清掃頻度
日常清掃・定期清掃・専門業者清掃の3段階
実務上、グリストラップの清掃は次の3段階に分けて管理するのが一般的です。
- 日常清掃:バスケット(生ごみ)を毎日取り除く
- 定期清掃:油脂分(スカム)を週1〜2回程度除去
- 専門清掃:槽の底に溜まった汚泥を月1回〜数ヶ月に1回、専門業者による吸引・洗浄
※店舗ごとに適切なタイミングで行う
ただし、これらはあくまで一般的な目安であって、業種や営業形態によって最適な頻度は異なります。
たとえば、揚げ物や炒め物を多く扱う業態では油分が多く、グリストラップ内に固着する油脂も早く増加します。
さらに、うどんやお好み焼きの生地などに使われる小麦粉は、排水中で水や油と混ざることで粘着した汚泥となり、清掃が遅れると固化して配管詰まりを起こすこともあります。
さらに詳しくグリストラップの清掃方法を知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
また、回収した汚泥は産業廃棄物であり、廃棄物処理法によって専門業者による回収も明確に定められているため、注意が必要です。
※業種別の注意点が気になる方はこちら
タカヤマのグリストラップ清掃管理サポート・公式ページはコチラ
- タカヤマ
【厨房・グリストラップ清掃】 - 全国一元管理
サポート 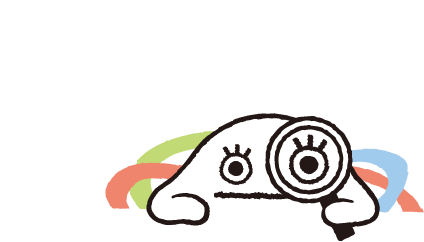
清掃を怠ることで発生するリスク
- 排水詰まりによる厨房機能の停止
- 悪臭・害虫による衛生指導
- 排水基準超過による指導
- 設備劣化による高額な修繕費
また、近年はフードデリバリーやテイクアウト需要拡大による厨房の稼働率上昇に伴い、清掃頻度の見直しが必要な店舗が増えています。
まとめ|日常管理を見直し、法に則った店舗運営を
グリストラップ清掃は衛生管理のためだけではなく「法令遵守」にも直結すると言えます。
法律で明確に日数規定されているわけではないものの、排水基準を満たす責任が課されていることはしっかりと理解しておきましょう。
一方で、チェーン店本部が全店舗のグリストラップ清掃の実態や厨房の衛生環境を把握することは至難の業です。そのため、全店を一元管理するシステムを持つ専門業者へのアウトソーシングの検討をオススメします。
タカヤマでは、厨房やグリストラップ、除害施設などの清掃や廃棄物収集・処理、排水設備の維持・メンテナンス作業と、それら契約に関わる情報を一元管理できるクラウドシステム「MIERU」を提供しています。
ぜひお気軽にご相談ください。
グリストラップ定期清掃のご相談・緊急対応のお問合わせはコチラ