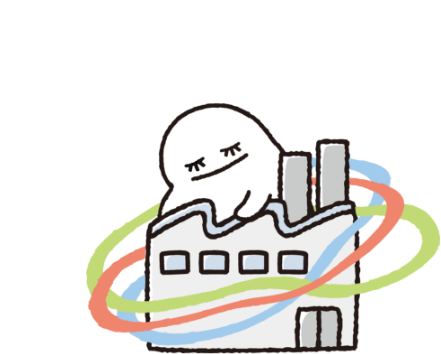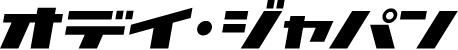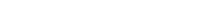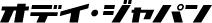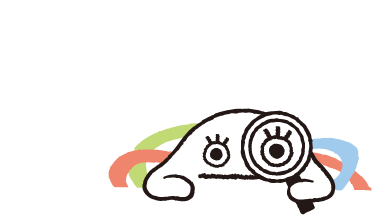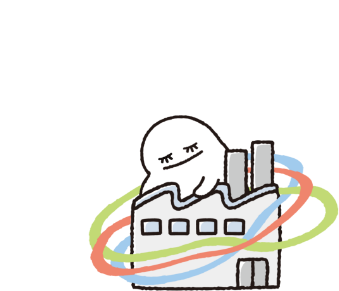排水処理施設で広く採用されている「接触酸化槽」。
省スペースで安定した処理が可能ですが、適切な維持管理を行わなければその性能は低下してしまいます。本記事では、接触酸化槽の仕組みやメリット・デメリット、維持管理の重要性について解説します。
Menu
接触酸化槽とは?
基本的な仕組み
接触酸化槽は、槽内に「担体」と呼ばれる接触材を入れ、その表面に微生物を付着させて排水中の有機物を分解する仕組みの処理設備です。
槽内で活動する好気性微生物は、曝気(ブロワー)から酸素が供給されることで活発に働きます。
そして、バイオフィルムと呼ばれる微生物の層が形成されることで有機物を分解し、安定した処理が可能となります。
構造の特徴
多くの接触酸化槽は、複数の槽を直列に並べて段階的に処理する構造になっています。
担体(接触剤)にはプラスチックや繊維素材が使われ微生物が効率的に定着する仕組みとなっており、微生物が住む容積が増えるため、処理能力を確保しながら小スペースで設置・運用が可能です。水質や流入量が変動しても比較的安定した処理が可能な点も特徴のひとつです。
 実際の接触剤の例。素材が異なっても役割に違いはありません。
実際の接触剤の例。素材が異なっても役割に違いはありません。接触酸化槽のメリット
処理が安定しやすい
活性汚泥法に比べて微生物が担体にしっかり固定されているため、急な水質変化や流量の増加に強く、処理性能が安定します。
省スペースで設置可能
微生物を効率的に維持しておくことができるため、同等の処理能力を持つ活性汚泥法の設備よりもコンパクトな設計になっていることが多いです。
都市部などの敷地が限られる施設に適しています。
運転管理の負担軽減
活性汚泥法では汚泥濃度の細かな管理が必要ですが、接触酸化槽は微生物が担体に固定されているため、日常的な管理の負担が軽減されます。
接触酸化槽のデメリット
担体や槽の詰まりリスク
微生物が過剰に増殖すると、担体(接触剤)同士が絡まったり目詰まりするなどの問題が発生します。水の流れや曝気効率の低下を招く要因になります。
余剰汚泥の処理が必要
微生物は時間が経つと剥がれ、余剰汚泥として沈殿槽内に流れ出します。これを沈殿槽で捕捉・処理しなければならず、余剰汚泥の徹底的な管理を行う必要があります。
定期的なメンテナンスが必須
長期間運転すると担体にスケールや不均一なバイオフィルムが付着し、処理効率が下がります。定期点検や清掃を怠るとトラブルの原因となります。

活性汚泥法との比較
接触酸化槽と活性汚泥法はいずれも代表的な生物処理方式ですが、特徴は異なります。
活性汚泥法
処理能力と不可変動への対応力の高さがありますが、汚泥濃度管理や沈殿槽の性能維持が難しく、広い設置スペースが必要です。小〜中規模で変動負荷がある施設でも活用可能です。
接触酸化槽
安定性・省スペース・運転の容易さが魅力ですが、詰まりや汚泥処理、定期点検の負担が課題です。
排水処理施設の緊急対応はこちらから
接触酸化槽がオススメな施設とは?
中小規模の工場や製造施設
敷地が限られており、省スペースで安定した処理を求める場合に最適です。
商業施設や大型店舗
水質や流量が比較的安定している環境では、簡易管理で運用可能です。
維持管理の重要性
点検や清掃を怠った場合のリスク
接触酸化槽は微生物が担体に定着しているため安定性は高いものの、定期点検を怠ると詰まりや処理不良、悪臭の発生などを引き起こします。
あまりにも酷い時には放流水の基準を満たせなくなり、施設の営業に影響する可能性もあります。
点検・清掃の頻度目安
基本的には、水量や曝気の状態、異臭の有無などを週1回程度確認することが望まれます。
その上で半年に一度は専門業者による点検を実施し、担体の状態やスカムの堆積、曝気装置の性能をチェックすることが望ましいです。
これにより大きなトラブルを未然に防ぐことができます。
装置交換の必要性
担体(接触剤)や曝気装置などは長期使用で劣化します。性能低下が見られる場合は交換を検討することが重要です。
接触酸化槽に関連する清掃や接触剤交換の具体的方法については、こちらの記事をご確認ください。
まとめ|専門業者の定期メンテナンスの活用が重要!
接触酸化槽は、省スペースで安定した処理が可能な優れた方式です。運転管理が比較的容易な一方、詰まりや余剰汚泥処理といった課題も存在します。
日常的な点検と定期的な専門業者によるメンテナンスを組み合わせることで、長期的に安定した運転が可能になります。
タカヤマでは、排水処理に関わる総合的なメンテナンスサービスを展開。公式ページはこちら
- タカヤマ【排水処理施設・設備】
- メンテナンス&エンジニアリング