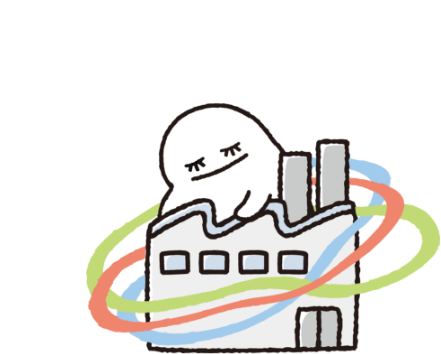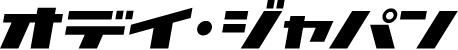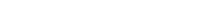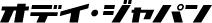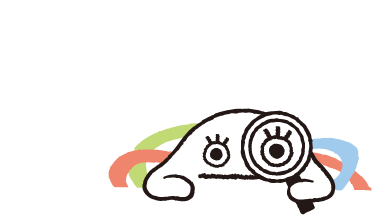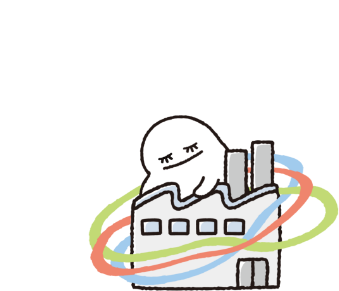接触酸化槽は安定性に優れた排水処理方式ですが、定期的な清掃や装置交換を怠ると処理性能が低下します。
微生物が定着した担体や曝気装置は、長期間の運転で汚れや劣化が生じるため、日常点検や定期メンテナンスが欠かせません。
本記事では、接触酸化槽の清掃や装置交換の手順、頻度の目安、作業時の注意点について解説し、安定した運転を維持するためのポイントを紹介します。
Menu
接触酸化槽の清掃とメンテナンスの重要性
接触酸化槽は微生物が担体(接触剤)に付着して安定した処理を行う仕組みですが、長期運転すると担体や槽内にスカムや汚れが蓄積します。これを放置していると目詰まりやバイオフィルムの不均一化が起こり、処理能力の低下や悪臭発生、放流水基準未達のリスクが高まります。
一方、定期的な清掃と装置交換を適切に行うことで処理性能の安定化・長寿命化・運転管理の負担軽減が可能です。
『接触酸化槽とは?』については、こちらの記事をご覧ください。
基本的な点検と簡易清掃
点検内容
簡易清掃のポイント
汚泥貯留槽のトラブル発生!緊急の場合はこちら
定期清掃の手順
清掃の頻度目安
施設の規模や負荷条件、担体の種類、曝気方式などで大きく条件は異なりますが、最低でも半年〜1年に1回程度の定期清掃が推奨されます。
清掃手順の概要
-
1.槽内の水を一部排水し、作業スペースを確保
-
2.担体の取り出しと洗浄
高圧水やブラシで汚れ・バイオフィルムを除去
3.槽底のスカムや堆積物除去
-
4.曝気装置の点検・清掃
-
5.担体を槽に戻し、運転再開
※作業は必ず安全管理・設備専門業者の指導のもと行うことが推奨されます
交換が必要な装置・部品
交換するタイミングは、メーカー推奨や運転年数を目安に判断します。
可能な限り専門業者に相談し、適切なタイミングで交換しましょう。

清掃・交換時の注意点
清掃や装置交換の作業中は、微生物の過剰除去に注意が必要です。
担体やバイオフィルムを必要以上に取り除くと、処理性能が一時的に低下することがあります。
また、槽内の水位や流量を適切に管理しないと作業中に事故や設備への負荷が発生する可能性があります。
さらに、高圧水や化学薬品を使用する場合は、必ず安全装備を着用し、作業計画に沿って手順を守ることが重要です。安全性と処理性能の両立を意識しながら作業を進めましょう。
清掃・交換の効率化のポイント
負荷変動が大きい工場などの場合は、定期的に清掃頻度の見直しも行う
まとめ|安定運転に欠かせない3つのポイントとは
接触酸化槽の安定した運転のためには、基本点検と定期清掃・装置交換が不可欠です。
専門業者と連携し、計画的なメンテナンスを実施することで、施設の稼働を安定させ、長期的な運用コストも抑えられます。
信頼できる専門業者と、ともに管理する意識を持つようにすることがオススメです。
排水処理施設の水槽管理はタカヤマにご相談を。公式ページはこちら
- タカヤマ【排水処理施設・設備】
- メンテナンス&エンジニアリング