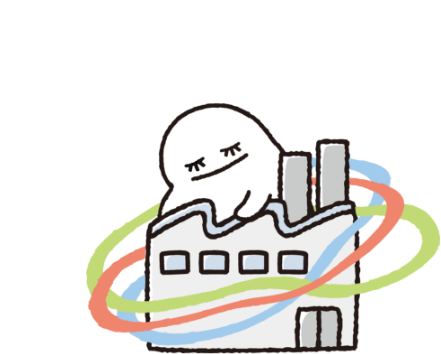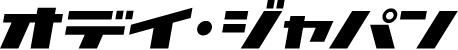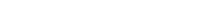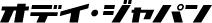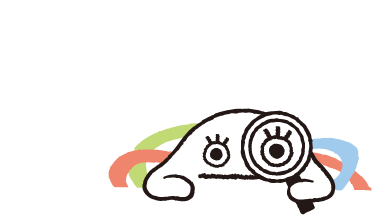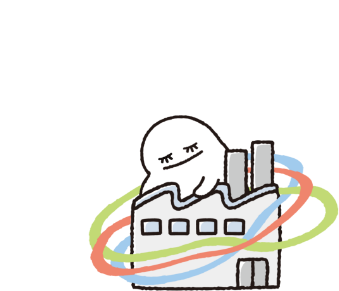排水処理施設を安全かつ効率よく運転するために欠かせない「流量調整槽」。
でも、「流量調整ってなに?」「どんな働きをしているの?」
と疑問に思う方も少なくないのではないでしょうか。
この記事では、排水処理に関わる事業者の方や施設運営を担う管理者の皆様に向けて、
流量調整槽の仕組みと役割をわかりやすく解説します。
Menu
1.流量調整槽とは?基本の仕組みをやさしく解説
1-1.そもそも流量調整槽とは?
流量調整槽とは、排水を一時的に貯めて流量を一定に保つことで、
排水処理設備への過負荷や処理効率の低下を防ぐための水槽です。
時間帯や作業内容によって変動する排水量を調整し、
次の工程(ばっ気槽など)へ安定的に水を送る役割を担っています。
流量のムラをならすことで、設備トラブルや処理不足のリスクを減らし、
排水処理全体の安定運転を支える大切な装置です。
1-2.流量調整槽はどこにある?施設内での位置づけ
排水処理施設では、原水(処理前の排水)がまず「原水槽」に入り、
スクリーンという装置で粗いゴミなどが除かれたあと、「流量調整槽」に送られます。
そして、水量を調整された排水が「ばっ気槽」やその先の処理工程へと流れていきます。
つまり、原水槽とばっ気槽の“間”に設置されている装置が流量調整槽です。
1-3.流量調整の仕組みは?ポンプやセンサーが活躍!
流量調整槽には水中ポンプやフロート(浮き玉)センサーなどが設置されており、
排水の量が一定になるよう調整して、自動的に次の工程に送り出す仕組みになっています。
たとえば排水が多い時間帯は、いったん流量調整槽に貯めておき、
センサーの指示に従ってポンプが起動し、
定量ずつばっ気槽へ送ることで処理がスムーズに行えるのです。
流量調整槽がおかしい!?緊急の場合はこちら
2.流量調整槽の役割|排水処理の“安定運転”を支える存在
2-1.ばっ気槽を守る「前さばき」の重要な役目
ばっ気槽では、微生物の働きによって排水中の汚れを分解しています。
しかし、急に排水が大量に流れ込むと微生物の働きが追いつかず、
分解処理がうまく進まない原因となってしまいます。
そのため、ばっ気槽に入る水の量をコントロールする
「前さばき役」として流量調整槽が重要な働きをしているのです。
2-2.排水量のムラをならしてトラブル予防
商業施設や工場では、使用する水の量が時間帯によって大きく変動します。
たとえば食品加工工場では、洗浄作業のタイミングで
一気に大量の排水が発生することがあります。
このとき、流量調整槽がなければ、ばっ気槽の処理装置に過負荷がかかって
故障や逆流が発生するリスクもあります。
流量調整槽は、こうしたトラブルのリスクを未然に防ぐ“緩衝役”としても機能。
排水処理施設全体の処理効率向上や安定運転に貢献しています。
3.まとめ|流量調整槽の理解が“管理力”を高める

3-1.点検・管理のポイントをおさえておこう
流量調整槽の役割を理解した上で、定期的な点検や清掃が欠かせない設備であることも忘れてはいけません。
フロートスイッチやポンプの動作確認、汚泥の除去などをしっかり行うことで、トラブルを未然に防げます。
3-2.わかれば納得、処理効率と安全性アップ!
流量調整槽は目立たない存在ですが、排水処理全体を安定させる縁の下の力持ちです。
施設管理の担当者がその役割をきちんと理解していれば、処理効率の改善や緊急対応の早期判断にもつながります。
“なぜ必要か”がわかれば、毎日の管理の意味も見えてくるはずです。
こちらの記事では、流量調整槽の維持管理や清掃についてまとめています。
あわせて、是非ご一読ください。
タカヤマでは、排水処理に関わる総合的なメンテナンスサービスを展開。公式ページはこちら
- タカヤマ【排水処理施設・設備】
- メンテナンス&エンジニアリング